レッスン音のMix論
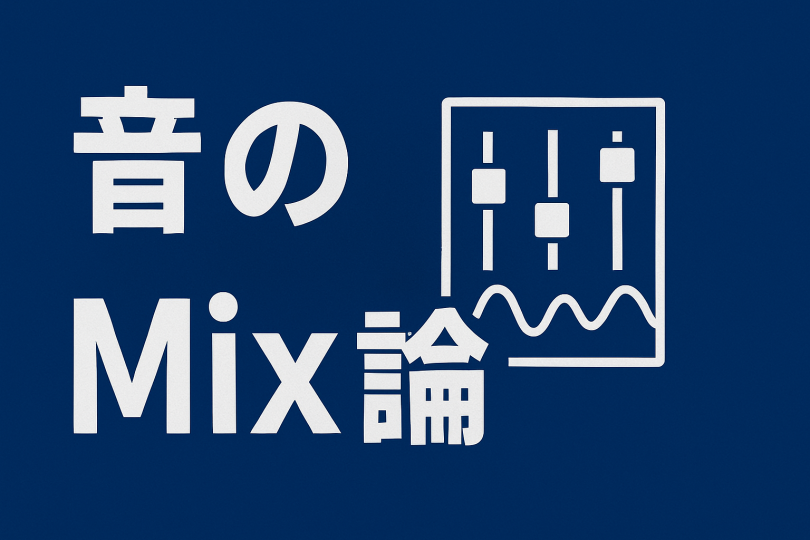
このレッスンを受講するには
本講座は、動画制作における音の扱い方を体系的に学べる入門講座です。dBの基礎から始まり、音量バランスの調整法、効果音の種類や挿入の原則、映像との一致感の作り方、展示会での音響対策まで幅広くカバー。さらに、高音・低音の聞こえ方や年齢による聴覚の違いなど、視聴者に配慮した音づくりの知識も身につきます。聞きやすく、印象に残る音演出を学びたい方に最適な内容です。
このレッスンが含まれる
月額見放題
全12パート順番に学習をすすめてください。
このレッスンについて
dBとは?
音の大きさを数値で表す「dB(デシベル)」の基礎知識を学びます。ミックスの前提となる音量の感覚を数値で理解するための第一歩です。
音量調整の重要性
音量が揃っていないと聞きづらく、視聴者にストレスを与えます。動画における適切な音量バランスのとり方を実例と共に解説します。
効果音の種類
効果音にはどんな種類があるのかを分類し、それぞれの役割や使いどころを具体例を交えて紹介します。演出の幅が広がります。
効果音の挿入の基本原則
効果音を入れる位置やタイミングにはルールがあります。視覚と音の一致、視聴者の注目ポイントに合わせた挿入の基本を学びます。
効果音とエネルギー保存の法則
映像の勢いや強弱に対して、効果音の「重さ」や「音圧」をどう合わせるか。視覚的エネルギーと音の整合性について考えます。
動きと効果音の一致の原則
映像内の動きと効果音のタイミングがズレると違和感が生まれます。自然で心地よい一致感をつくるための原則を解説します。
効果音のパターンの統一
複数の効果音を使う場合、統一感がないとノイズになります。種類・音質・リズムなどを揃えるコツを実例付きで学びます。
展示会上映のテクニック
展示会やイベントなど環境音が多い場で、動画音声を聞き取りやすくする工夫を紹介。ナレーション・効果音・BGMのバランス調整が鍵です。
音声チェック時の環境について
音のバランス確認は再生環境によって印象が変わります。スピーカーやヘッドホン、音量の違いによる聞こえ方の変化を解説します。
イヤホン難聴の予防
イヤホンやヘッドホンで長時間作業する人のために、聴力を守るための音量設定や作業時間の目安など、実践的な予防策を紹介します。
高音と低音での聞こえの違い
人はすべての音域を同じように感じているわけではありません。高音・低音の聞こえ方の違いを踏まえたミックスの工夫を学びます。
年齢による聞こえの違い
年齢によって聞き取りやすい音域は変化します。全年齢に伝わる音作りのために、世代間の聴覚特性を踏まえた配慮を解説します。
各パートについて
-
1dBとは?
-
2音量調整の重要性
-
3効果音の種類
-
4効果音の挿入の基本原則
-
5効果音とエネルギー保存の法則
-
6動きと効果音の一致の原則
-
7効果音のパターンの統一
-
8展示会上映のテクニック
-
9音声チェック時の環境について
-
10イヤホン難聴の予防
-
11高音と低音での聞こえの違い
-
12年齢による聞こえの違い
不明点があれば、こちらのフォームより質問をお願いします。登録されているメールあてに回答をさしあげます。
